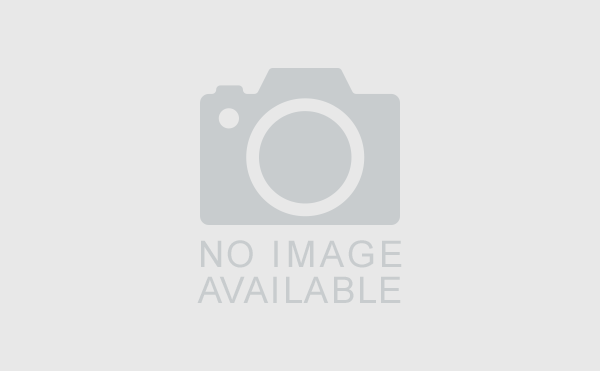【創作折り紙のやり方】第1回/鶴の基本形から始める。
皆さん、こんにちは。
折り紙へ続く道へようこそ。
この記事は
こんな悩みを持つ方へ向けた記事です。
・創作折り紙のやり方がわからない。
・創作折り紙は難しそう、できるか不安
こういった疑問に対して
私なりの方法を紹介します。
本記事の内容です。
私の折り紙歴は20数年
(ちょいちょいブランクありますが・・・)
これまでに、約100作品の創作折り紙を
自身のSNSに投稿してきました。
私が頻繁に用いている創作方法を
数回の記事に分けて解説します。
<注意点>
創作方法は沢山あります。
私が発信する情報が全てではありません。
一例として参考にしていただければ嬉しです。
それでは、本題に進みましょう。
1.初歩的な創作折り紙
1)創作に必要な手順
①テーマを決める
②構造を考える
③展開図を書く
・後で書く場合もある
・書かない時もある
④基本形を折る
⑤仕上げる
初心者の方にとっては
〝④基本形〟に至るまでが非常に困難です。
では
テーマに見合った基本形を
作ることができなければ
創作折り紙はムリなのでしょうか?
そんなことは、ありません。
既存の基本形を使えばよいのです。
2)既存の基本形?
例:鶴の基本形
写真をご覧ください。

「鶴」です。
途中の形
これを鶴の基本形といいます。

上のカドは「羽」
下のカドは「顔」と「尾」になります。

このように
完成形に必要なカドが折り出される状態を
「基本形」といいます。
つまり
「鶴」も創作作品も、折る時のプロセスは同じ
「基本形」に畳む ⇨ 仕上げる
です。
ところで
鶴の基本形は
「鶴」しか作れないのでしょうか?
そんなことは、ありません。
試しに簡単な創作の例をご覧ください。
2.「何を作るか」ではなく「何に見えるか」
鶴の基本形を
様々な角度から眺めてみてください。
色々な形が見えてきます。
私が即興で考えた創作の例をご覧ください。
創作例①/小鳥
まず、鶴の基本形を作ります。

カドを写真のように折ります。

中心線で半分に折ります。

首と顔は「かぶせ折り」
足は「中わり折り」を2回繰り返します。

足を細く折り
シッポを短くして出来上がり

基本形は鶴ですが
仕上げを工夫すると
見栄えが異なる作品を作ることができます。
創作例②/ハチドリ
「広げてつぶす」感じで
写真のように折ります。

顔は「かぶせ折り」
くちばしを細く加工しました。

創作例③/エビ
鶴の背中になる部分を小さくします

腕を引き出し
尾(腹部?)に「段折り」を加えます。

創作例④/ダチョウ
創作例①の小鳥と同じ要領です。
写真を見ながら仕上げてみましょう。
これを「にらみ折り」と言います。

創作例⑤/インコ
これも「にらみ折り」してみましょう。

このように
「基本形」から様々な形を連想することから
始めてみましょう。
他にも様々な形を
作り出すことができるはずです。
ご自身で色々試してください。
初歩の段階で大切なことは
「何を作るか」ではなく「何に見えるか」
です。
出来栄えなど気にする必要はありません。
様々な表現をしましょう。
上手くいかないことも多いと思います。
ぜんぜんOKです。
ボロボロになるまで紙を
「いじり続ける」ことが近道だと思います。
3.今回のテーマを応用した創作作品の紹介
拙作より、少し難易度の高い
鶴の基本形から作られている作品を
ご紹介します。
1)飛竜
難しすぎず、そこそこリアルなドラゴン
バランスよく仕上がったと自己評価。
作品名:飛竜折り方:不切正方形一枚用紙:24×24cm(トーヨー)創作・折手:私ツルの基本型から作ったシンプルなドラゴンです。
2)マンモス
特徴を大げさに捉える表現(ディフォルメ)で
マンモスを作りました。
「鶴の翼の部分」をキバに見立てています。
最後に
いかがでしたか?
一例としての
「創作の入り口」を示してみました。
記事の冒頭でも述べましたが
誤解のないようにもう一度述べておきます。
創作折り紙の方法は、たくさんあります。
この記事の内容が全てではありません。
しかしながら
「とりあえず、やってみたい」
と思う方のキッカケになれば嬉しいです。
次回以降も鶴の基本形を主人公に
応用編を書いていこうと思っています。
最後まで読んでいただき
ありがとうございました。
(@^^)/~~~
⇩こちらも鶴の基本形から作った作品です⇩
youtaiyamaguchi.hatenablog.com
youtaiyamaguchi.hatenablog.com